医師事務作業補助者として働き始めたばかりの頃は、
「先生にどう声をかけたらいいんだろう」
「いつも忙しそうで話しかけづらい…」と感じることが多いですよね。
医師とのコミュニケーションは、慣れるまでは緊張するもの。でも、少しずつコツをつかめば必ずうまくいくようになります。
この記事では、医師との信頼関係を築くために知っておきたい考え方や、現場で役立つ話し方のポイントを解説します。
日々の業務が少しでもスムーズに、そして自信をもって医師と関われるようになるヒントをお届けします。
医師とのコミュニケーションがなぜ大切なのか
医師事務作業補助者の仕事は、単に医師の指示を受けて書類を作成するだけではありません。
外来診療の流れをスムーズにし、医師が診療に集中できる環境を整える「サポート役」としての役割もあります。
そのためには、医師とのコミュニケーションがとても大切になります。
どんなにパソコン操作が得意でも、医師の意図を理解できなければ正確な文書は作れませんし、診察の流れを止めてしまうこともあります。
医師は常に多くの患者さんを診ながら、次々と治療に対する判断をしています。
そんな中で、短い時間でも必要な情報を正確に伝える力が求められます。
「今、このタイミングで声をかけても大丈夫かな?」
「先生はどんな意図でこの指示を出したのだろう?」
そんな小さな気づきや配慮が、信頼関係につながっていきます。
医師とのコミュニケーションがうまくいく人の特徴
医師との関係がうまくいっている医師事務作業補助者には、いくつかの共通点があります。
まずひとつは、観察力がある人です。
医師の表情や話し方、行動、診察の進み具合等をみて
「今、話しかけるべきか」
「もう少し待ったほうがいいか」
自然に判断できる人は、医師からの信頼を得やすいです。
次に、報連相(報告・連絡・相談)のタイミングが適切な人。
報告をまとめて後で伝えるのではなく、「今伝えるべきこと」を見極めてタイミングよく声をかけられる人は、業務の流れを止めません。
言葉のやり取りだけでなく、表情や行動、気づかいも大切なコミュニケーションの一部です。
言葉遣いや表情がやわらかい人は、相手に対して安心感を与えます。
医師は忙しく、ピリピリした雰囲気になりがちです。そんなときでも穏やかな声で伝えられる人は、職場の空気を和らげ、安心して仕事を任せられる存在になります。
実際に現場で役立つ!医師とのコミュニケーションのコツ
では、実際の現場でどのようにコミュニケーションを取ればよいのでしょうか。
「結論から伝える」ことを意識する
医師は時間に追われています。報告や相談をするときは、まず「結論」→「理由」→「補足」の順に伝えるとスムーズです。
「〇〇さんの検査結果が出ました。先生の確認が必要です。」
「〇〇さんの採血、まだ行っていません。今から実施でよろしいでしょうか?」
「紹介状の内容を一部修正しました。ご確認をお願いいたします。」
どれも最初に“結論”を伝えることで、医師がすぐに状況を把握でき、判断のスピードが上がります。
わからないことはそのままにしない
医師の指示が聞き取れなかったり、内容が曖昧な場合は、遠慮せず確認しましょう。
間違ったまま進めるより、質問する方が信頼されます。
例:「先ほどの指示について、〇〇という内容でよろしいでしょうか?」
「ありがとう」を伝える習慣をもつ
医師への感謝を言葉にするのは意外と大切です。
「ご指示ありがとうございました」
「確認いただいて助かりました」などの一言が、日々の関係を良好にします。
医師の働き方を理解する
医師は専門的な業務のほかにも、説明や書類作成など多くの負担を抱えています。
「医師がどんな業務に追われているか」を理解して動けるようになると、自然とコミュニケーションもうまくいくようになります。
信頼される医師事務作業補助者になるために意識したいこと
コミュニケーションは、経験を重ねることで確実に上達します。
最初から完璧を目指す必要はありません。
大切なのは、相手を理解しようとする姿勢
間違いを素直に認めて修正する姿勢
一歩先を考えて動く意識
これらを少しずつ積み重ねることです。
信頼できるクラークになると、自然と業務を任せてもらえるようになります。
そうなると仕事の幅もどんどん広がっていきます。
コミュニケーションは単なる会話のテクニックではなく、「チーム医療の一員として支える力」です。
相手を理解しよう、役に立ちたいという気持ちがあれば、必ず信頼関係は育っていきます。
焦らず、毎日の中で少しずつ医師との関係を築いていきましょう。


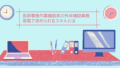
コメント